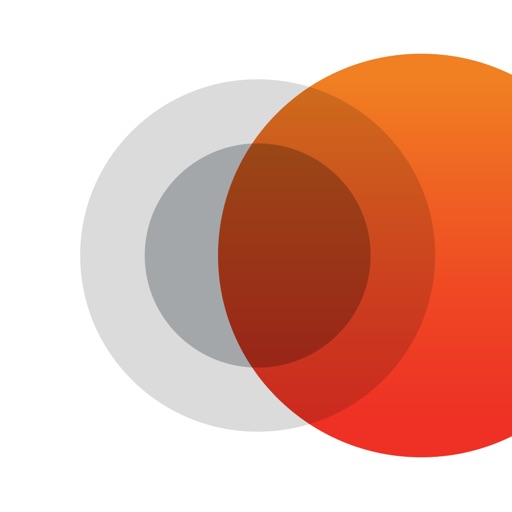皆既月食をカメラで撮ろう!
数年に一度のレアな天体ショーである皆既月食が2022年11月8日にやってきます!
皆既月食はおよそ1時間程度で刻々と月の大きさ(明るい部分)が変わっていき、その後非常に暗い赤い月(ブラッドムーン)が見えてくるため、ふだんの月の撮影よりもやや難易度が高い撮影になります。
過去に私が撮影した皆既月食を参考にしながら、事前に準備するものと当日の流れ、撮影に必要なカメラの設定値などを確認してみましょう。
スマホで撮影するのはなかなか厳しいですが、試してみる価値はあるかも。iPhoneやAndroidスマホでチャレンジしたい人むけの記事も更新しました → iPhone、スマホで満月、皆既月食をクレーター模様まで撮る方法!アプリが重要だよ!
動画でも解説してます!
YouTubeのstudio9 channelでも月食の撮り方の解説をしました!過去の月食の実データを使いながらターコイズフリンジの合成手順なども紹介していますよ!良かったらチャンネル登録してね!
2022年11月8日 月食スケジュールと事前に準備するもの
まずは皆既月食当日のスケジュールを確認しておきましょう。
皆既月食は19:16~20:42の1時間以上!
今回の月食は欠け始めから皆既月食、そして欠け終わりまで夕方の観察しやすい時間帯で日本中で見ることができます。
食の最大は19時59分。全国で観察可能!
月が欠け始めるのは程よく月が昇る18:09ごろで、ここから1時間くらいかけて少しずつ月が地球の影に入り欠けてゆきます。完全に影に入り皆既月食となる(皆既食のはじめ)のが19:16。
今回は条件が良いので皆既食は19:16~20:42と1時間以上じっくり赤い月(ブラッドムーン)を観察できます。食の最大は19時59分です。その後、また1時間ほどかけてゆっくりと元に戻り、月食が終わるのが21:49となります。
欠けはじめから欠け終わりまで3時間40分とゆったりとしたスケジュールで撮影ができますね。
東方向に高いビルなどがない開けた場所で観察しましょう。
事前に準備しておくものは?
月食を撮るためにはカメラと望遠レンズが必須で、赤い月を撮るなら三脚も必ず必要になります。他にレリーズやバッテリー、防寒対策など事前の準備も大事です。記事の後半に詳しくまとめていますので最後までご覧下さいませ。
スマホの場合、最近のiPhone14など望遠レンズが付いているタイプならもしかするとちょっと位撮れるかも知れませんが、基本難しいと考えましょう。
欠けてゆく月(明るい部分)を撮る場合
徐々に欠けてゆく月を撮る場合は結構簡単で、普通の月撮影のセッティングと同じです。下記のリンクに超詳しくまとめているので、ここでは簡単に手順だけ紹介します。
1.カメラをマニュアルモードにする
マニュアルモードだと急に難しく感じるかもしれませんが、大丈夫です。マニュアルモード(M)にして、決まった値を設定していくだけです。
オートやAv(A)など他のモードだと月が真っ白につぶれてしまったり、失敗する可能性が高いです。。
2.一番ズームして月にピントを合わせる
手持ちのレンズで一番望遠のレンズを装着し、月にピントを合わせます。カメラの設定はこのあと調整しますが、欠けはじめから撮影する場合はF8、ISO400、1/640にセットしておきます。
月を画面の真ん中に持ってくれば大抵は普通のAF(シャッター半押し)で合うはず。どうしても合わない場合はマニュアルフォーカス(MF)で合わせたり、AFで遠くの街明かりに合わせたあとにMFに切り換えてピントを固定してもOK。
3.欠け方に応じて設定を変えて撮る
月の月齢に応じた撮影設定と同じで、1時間の間に満月→新月へ遷り変わるだけと思っておけばOK。
だいたい次のような設定にしておけばOKです。皆既食から元の満月に戻る時も同じです。
| タイミング | ISO感度 | F値 | シャッター速度 |
|---|---|---|---|
| 欠けはじめ (満月) | 400 | 8 | 1/640 |
| 800 | 8 | 1/1250 | |
| 1/4欠けたくらい | 400 | 8 | 1/200 |
| 800 | 8 | 1/400 | |
| 半分欠けたくらい | 400 | 8 | 1/100 |
| 800 | 8 | 1/200 | |
| 3/4欠けたくらい | 400 | 8 | 1/60 |
| 800 | 8 | 1/120 | |
| 1600 | 8 | 1/240 | |
| 全部欠けるギリギリ (皆既食直前) | 400 | 8 | 1/50 |
| 800 | 8 | 1/100 | |
| 1600 | 8 | 1/200 |
*明るすぎて白飛びしてしまうと撮影後に補正できないため、安全を見て若干暗めに写るような設定にしています。
三脚使うならISO400、手持ちならISO800 or 1600
紛らわしくないようにF値はすべてF8にしておきました。三脚を使っている人ならISO400の設定を使うのがおすすめ。
手持ちで頑張りたいならISO800またはISO1600の所を参考にしてみて下さい。とりあえず下の表の値をそのまま入れるだけOKです。(もちろんここから各自F値を変えながら調整してもOK)
ホワイトバランスはとりあえずオートでもOKですが、個人的には寒色系の(白色)蛍光灯なんかもおススメ。めったにないチャンスなので念のためRAW+JPEGで記録しておきましょう。
空がまだ明るい場合
もし、まだ空が明るい時間帯であれば上記リンクで紹介した値では明るすぎるかも。その時は暗くする設定(F値を大きくする or シャッター速度を速くする or ISO感度を小さくする)をお試し下さい!1~2段は変動しているかも知れません。

以前撮影した空が明るいときの月(10月の午後4時ごろ)。明るい部分が小さく、暗い空と同じF8, 1/120, ISO800くらいの設定で撮ると明るすぎました。。(現像時にシミュレーション)今回は日の入り近くでここまで明るくなるとは思いませんが、表のままだと思ったより明るくなる可能性が高いです。

上と同じ月を明るい満月向けの設定(F8, 1/800, ISO400)で撮ったところちょうど良くなりました!
5.あとは撮るだけ!
望遠にすればするほど手振れを起こしやすいので、できれば三脚を使いましょう。
どうしても手持ちで撮影する場合は上記のISO800や1600の設定で、しっかり構えて優しくシャッターを押すこと。もちろん手振れ補正はONにしておきます。*三脚の場合は手ブレ補正OFF推奨
全然大きく写らないじゃん!と思うかもしれませんが、このくらいのサイズで取れれば上等です。後でトリミングして大きくします。ちなみにこちら冒頭の写真のトリミング前の写真。EOS 7D (APS-Cセンサー)に280㎜のレンズで撮りました。
↓このくらい大きく写れば十分です!
ここまで写ればあとはPCに送って空の暗い部分をトリミングすればOK。スマホやカメラ内でトリミングしてもいいですね。
この設定だと赤い月は写らないよ!
上記設定は明るく見えている月の部分がキレイに写るための設定なため、赤い月はほとんど写りません。
皆既月食ならではの赤い月(ブラッドムーン)を撮りたい場合はこの後紹介する設定をためしてみてください。
6.明るさ(露出)を微調整
設定が間違っていなければ、これで月のクレーター模様までしっかり映ってるはずですが、多少の明るい、くらいはあるはず。
明るいなと思ったら、ISOを下げる、F値を大きくする、シャッタースピードを速くするのどれかを設定して撮り直します。1~3目盛(1/3~1EV)程度変えれば適正になるはず。
暗いなと思ったら、明るいときの逆(ISOを大きくする、F値を小さくする、シャッタースピードを遅くする)の設定をします。
例えば、満月をISO400、F8、1/640で撮ってみて暗いなぁと思ったら、シャッタースピードのダイヤルをカチカチと動かして、ISO400、F8、1/400にすると良い明るさになると思います。(シャッタースピードが遅いと光がたくさん入ってくるので明るくなる)
もちろんF値を8⇒5.6としても明るくなります。(F値は小さくすればするほど光を多く取り入れる)。
この辺の調整をうまくやりたいけど、F値とかISO感度とかよく分らん、、という人は下記ページを予習しておきましょう。
*カメラや現像ソフトによっては色温度(ホワイトバランス)によって明るさの見え方がかなり変わることがあるかも知れません。私の環境だとオレンジ系の色(太陽光、曇り、日陰)で撮ると暗くなって、白~青系の色(蛍光灯、白熱電灯)だと明るめに出てくる感じです。
欠けた部分(赤い月、ブラッドムーン)を撮る場合
月が地球の影に入って明るい部分が見えなくなってくると、影の部分が肉眼でも赤く見えてきます。
赤く見えている部分は影なので、明るい部分よりもかなり暗く、上記の明るい部分用の設定をしてもほとんど見ることはできません。
よって、赤い月(ブラッドムーン)を撮るなら特別な設定が必要です。
ISO3200, F6.3~8, 1/10
赤い月の撮影は私も経験が浅いのですが、2014年の皆既月食の結果からみると、カメラの設定を「ISO3200, F6.3, 1/10秒」~「ISO3200, F8, 1/10秒」程度に撮影しておくのが良さそうです。
下記は「ISO3200, F6.3, 1/10秒」で撮影した例です。
1/10秒より長いとブレるかも
月は非常にゆっくりと動くためほぼ止まっているように見えますが、超望遠レンズで月を見ると目視でもすこしずつ動いている様子が分かるほどの「動体」です。ですので、暗いからといってシャッタースピードを秒単位まで伸ばすと月がブレてしまい月の模様がハッキリ写りません。
こういう時はF値を小さくしたいですが、通常の望遠レンズはF6.3くらいまでしか小さくできないため、あとはISO感度を上げて対応するしかありません(もしくは赤道儀を使うか)。
月の動きを止めたい場合は1/10秒を目安にしてみると良いでしょう。ブレをあまり気にしないなら1/5(0.2秒)くらいでも良さそうです。
よほどしっかりした三脚を使わないと超望遠域の撮影では風や周りで人間が動くといった僅かな振動も影響が出てきます。ほかにシャッターショック、ミラーショックなどの影響も加わるため、普通の(高級なガッチリしたものでない)三脚を使う場合は早めのシャッタースピードを使うのが良いです。
*しかも、後でトリミングするのでブレがさらに大きく見えてしまいます
三脚を設置する場所も芝など柔らかい場所ではなく、コンクリートなど硬くしっかりした場所が良いです。
約3年半前の2014年の皆既月食と比べて、現在はカメラの高感度性能もかなりアップしているため今の入門機でもこれ以上クリアな写真が撮れそうです。写真はEOS 7D(2009年発売)を使用。
高感度性能が高いカメラなら感度を上げて、シャッタースピードを速くする方向で調整すると良い結果になりそうな気がします。
暗い場合は感度を上げてみる
上の写真は皆既食になる直前でまだ明るい所が少し見えている状態なので月も結構明るい感じです。食の最大のタイミングではもう少し暗くなるかも。
上で説明したようにシャッタースピードを長くすると月がブレてしまうため、長くしてもせいぜい1/5秒くらいにして、感度をISO6400付近まで上げるのが良いのでは?と思います。
もちろんF値を8より小さい値にできるならできるだけ小さなF値にしておく方が良いですね。
白い部分と赤い部分の両立は難しい
上の写真をみても分かるように、月の明るい部分と影の赤い部分は非常に大きな輝度差があるため一度に捕らえることは非常に難しいです。赤い部分を撮ろうと思うと明るい部分は白飛びしてしまうし(下の写真の様に)、明るい部分に合わせると、赤い部分は暗くて潰れてしまいます(明るい部分を撮る設定)。
ダイナミックレンジの大きなカメラを使って、高速連写で大きな露出幅(5~6EVくらい)でブラケット撮影をしてからHDR合成などすれば赤い部分と白い部分を両立できますが、やや難易度が高い撮影だと思っておきましょう。
やるなら事前に練習した上で望みましょう。ターコイズフリンジの撮り方は後述します。
必ずレリーズ(or 2秒タイマー)を使う
三脚に据えているとはいえ、手でシャッターを押すとかなりの確率でぶれてしまうためレリーズやリモコンを使ってシャッターを切りましょう。
最近のカメラならスマホと接続して無線でシャッター切れるカメラも多いですよね。レリーズがなければカメラの2秒タイマーで代用しても良いです(ややブレる可能性はあり)
必要ならミラーアップ撮影を
一眼レフの場合、ミラーショックが起こる可能性があるのでできる方は、ミラーアップ撮影をしてもいいでしょう。ミラーアップ撮影なにそれ?という人はライブビューの状態でシャッターを切るとショックが少ないはず。
ミラーアップ撮影はしなくても致命的なミスにはならないので、分からなければスルーでも大丈夫です。
手ブレ補正はOFFにしておく
三脚を使った超望遠撮影の場合、手ブレ補正が誤作動してブレてしまうという可能性もあるため通常は手ブレ補正OFFにして撮影するのがおすすめです。
撮影後はONに戻しておくのを忘れずに。
RAW+JPEGで撮っておこう
皆既月食は滅多にないチャンスなので、撮影する場合はできるだけ良い状態のデータで撮っておきたいものです。普段JPEGで撮っている人もできればRAW+JPEGで撮影しておくのがおすすめ。
最近はコンデジやスマホでもRAW記録できるものが増えていますね。
将来画像調整をしたいという場合もRAWで記録が残っていればかなり柔軟な補正が可能です。RAWからJPEGは作れても、JPEGからRAWのデータは作れないので。
RAWってなに?という方は下記のページをどうぞ!
ターコイズフリンジの撮り方(やや上級)
部分月食中は影と明るい部分の間に「ターコイズフリンジ」という青っぽいラインが現れます。(地球の大気によるものだと聞いたことがあります)
上で説明した通り、影と明るい部分の輝度差が非常に大きく、明るい部分と暗い部分を両立させる必要があります。これは現在のカメラの性能を超えるため通常の撮影ではターコイズフリンジを撮るのはかなり難しいですが、露出ブラケット撮影をしておくと撮れますよ。
できるだけ露出をばらして撮影しておく
下の写真は2018年1月31日の皆既月食で撮影したターコイズフリンジ。この時はソニーα7R IIIの露出ブラケット(露出BKT)機能を使ってISO1600, F8, 1/125を中心に±4EVずらし9枚(9EVぶん)の露出違いの写真を撮っておき(もちろんRAWで)、これら9枚をLightroomでHDR処理して作りました。
どこまで露出幅をもって撮影するのが最適かどうかは見極められていませんが、数年に一度の貴重なシーンですので最高画質&最大露出幅で全カット撮影するくらいの準備をしていても良いと思います。
ソニーのカメラはかなり広い露出幅で設定できますが、キヤノンなどその他のカメラでも5EV分くらいは確保出来るはず。
上の写真を撮影したときの一連のカットはこんな感じです。
露出ブラケットしておけば雲と一緒に撮れる
月に露出を合わせると普通は周りの雲は暗くなって見えなくなりますが、ブラケット撮影するなら月と雲を両立させることも可能です。こんな感じで雲と月食を両立させられます。

2021年5月の皆既月食。これも±4EVずらし9枚(9EVぶん)で撮影し、LightroomでHDR合成したはず
事前に準備しておく機材
撮影に必要な機材はカメラ、レンズ、三脚のほか、季節柄防寒に関するものですね。ひとつずつ見てみましょう。
赤道儀など特殊な機材は使わず、初心者の人でもなんとか撮れるような内容にしています。
カメラ - 赤い月を撮るならやや高スペックが必要
一眼レフやミラーレスカメラのほか、高倍率ズームのデジカメ(コンデジ)でも撮影できます。
月の明るい部分を撮るのであればカメラの性能はそれほど高い必要はありません。レンズがどれだけズームできるか(望遠が効くか)の方が大事ですね。EOS Kissなど入門用一眼レフでも十分です。
ただし、赤い月はかなり暗いため高感度に強い最近のカメラがあると心強いです。入門機でも最近発売されたようなもの(EOS Kiss X10やα6400とか)なら大丈夫かと思いますが、5年以上前のものだとノイズがかなり出るかも知れません。ISO3200程度で酷いノイズが出ないものが目安です。
冒頭の赤い月はキヤノンの入門用一眼レフEOS Kiss X9(2017年発売)で撮影しましたよ!
ソニー ミラーレス一眼 α6400 ダブルズームレンズキット SELP1650 F3.5-5.6+SEL55210 F4.5-6.3 SEL55210 ブ...
スマホは厳しいかもだけど、試してみる価値はあり
スマホのカメラで撮影するのはかなり厳しいですが、iPhone14など最近の高級スマホはデュアルカメラで望遠側の画質も上がってきているため、画質にこだわらなければ撮れるかも。
スマホで撮る方法をは次のエントリーに書いたのでそちらを参考にしてみて下さい。
レンズ - できるだけ望遠のものを
月はとても小さいためできるだけ望遠のものを用意しましょう。最低でも35mm判換算で300mm程度のものを。できれば400mm以上は欲しい所です。
エントリー機のダブルズームキット付属の望遠レンズでもOKです。より大きく、キレイに撮りたい人は別途超望遠レンズを用意しましょう。メーカー純正の超望遠レンズは目が飛び出るほど高価ですが、シグマやタムロンのレンズはコスパが良く頑張れば手が届く範囲。
シグマやタムロンの150-600mm級のレンズは超望遠かつ普通の人にも手の届く価格帯ですね(600mm級のレンズはかつて数十万~百万円コースだった)。
ソニーのミラーレスならSIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporaryあたりはコスパ良いです。一眼レフユーザーならタムロン、シグマからでている150-600mmくらすのズームがおすすめですね。
TAMRON 超望遠ズームレンズ SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD キヤノン用 フルサイズ対応 A011E
なお、普通のズームレンズで望遠側が100mmくらいのレンズでは月は豆粒くらいの大きさにしか写らないので厳しいです・・・
私が作ったカメラバッグもおすすめです!
ちょっと宣伝ですが、上に挙げた150-600mmクラスの超望遠レンズは大きくてなかなか普通のカメラバッグには収まらないんですよね。。私が監修したカメラバッグ、Endurance Ext IIなら普通サイズのバッグで150-600mmや200-600mmクラスの超望遠レンズも収まるようになっているのでおすすめですよ!
---
APS-Cセンサーやマイクロフォーサーズの人は係数を掛ける必要があります。35mm換算ってなに?という方は以下のページを読んでみるのもおすすめ。
APS-Cセンサーのカメラ(入門~中級カメラ)
APS-Cサイズのセンサーを搭載したカメラ(キヤノン、ニコン、ソニー、ペンタックス、フジフイルムなどの[フルサイズ]ではないカメラ)は画角が35mm判(フルサイズ)の約1.5倍になるため、お持ちのレンズの焦点距離に1.5を掛けて読み替えて下さい。係数を掛けて300mm以上になれば十分撮影出来ます。
たとえばキヤノン EOS Kiss X9のダブルズームキットに入っている望遠レンズは55-250mmなので、250に1.5をかけると375mm相当。十分撮影可能ですね。(キヤノンのAPS-Cは1.6倍が正確だけど)
EOS Kiss X9に上記の150-600mmレンズを付ければ、1.5倍の約900mm相当の撮影が可能です。
マイクロフォーサーズのカメラ(オリンパス、パナソニック)
オリンパス、パナソニックなどのマイクロフォーサーズ機の場合は画角が35mm判(フルサイズ)の約2倍になるため、お持ちのレンズの焦点距離に2を掛けて読み替えて下さい。
たとえば、オリンパス E-PL8やOM-D E-M10 MarkIII ダブルズームキットに入っている望遠レンズは40-150mmなので、150mmに2を掛けて300mm。OKですね。
高倍率コンデジ
高倍率ズームのコンデジの場合、35mm判換算の焦点距離はメーカーの仕様に書いています。例えば、高倍率番長のニコン COOLPIX P950なら最大で2000mm相当の異次元の超望遠撮影ができるため月の撮影にもってこいです(ただし高感度にはあまり強くない)。
さらにCOOLPIX P1000という3,000mm相当の撮影ができるとんでもないやつまでいます。
光学15倍以上のカメラなら月をかなり大きく撮影できます。
三脚 - 赤い月を撮るなら必須
月が欠けてくると暗くなるため三脚があった方が無難です。欠けている明るい月の部分を撮るならなんとか手持ちでも撮影できますが、皆既食中の赤い月を撮るなら必須だと思って下さい。
超望遠レンズで撮影するためある程度しっかりした三脚が好ましいです。
最低でも1万円クラスのものを選びましょう(ほかの撮影でも使えます)。このクラスの三脚でも600mmなどの超望遠レンズを付けるとブレる事が多いので、できれば2~3万以上のさらにしっかりしたものを使いたいところ。
月食の撮影のためだけに新規で2~3万の三脚買う必要はないと思いますが。。
2,980円みたいな三脚でも使えないことはないですが、安定性に難ありという感じ。コンデジやマイクロフォーサーズなど小さなシステムならなんとかという感じです。
一眼レフ 三脚 K&F Concept カメラ三脚 軽量 アルミ合金製 コンパクト 一脚可変 自由雲台 デジタルカメラ ...
レリーズ
三脚を使った赤い月の撮影では必須だと思った方が良いです。超望遠撮影なので三脚を使っていてもカメラのシャッターボタンを使うとブレやすいです。
最近のカメラならWi-FiやBluetoothでスマホと繋いでリモートシャッターができるものも多いのでそれを使っても良いですが、事前に接続の確認をしっかりしておくこと。(寒いためバッテリーの消耗も激しくなります)
最悪レリーズも何もないという状況の場合はカメラの2秒タイマーで代用しましょう。
月の追跡アプリ
スマホを持っている方なら月の追跡アプリを入れておくと良いです。今まではMoon Seekerを使っていたのですが、今回改めて見たらSun Surveyorなるアプリがかなり良さげ。
月や太陽の出る時間、入りの時間、薄明の時間はもちろん、緯度や方角、カメラを向けるとARで実際の予想軌道を重ねてくれたり(ここまではMoon Seekerでもできる)、Googleマップのストリートビューで自宅にいながらロケハンできる超機能も付いているなど持っておくと便利。日本語にも対応しています。
特に今回の月食は緯度が低めなので月が建物に隠れないかどうかを事前にチェックしましょう。

31日夜のスカイツリー周辺の軌道を表示させたところ。地図上に表示させるだけでなく、ストリートビューを使って実際の風景に合成してシミュレーションできるところがすごい!(ただし、表示されている月は実際にはもっと小さいため、これと同じ絵が撮れるという訳ではない(と思う))
iPhone版が1200円、Android版が880円(執筆時)とまぁまぁ値の張るアプリですが、レンズに比べればタダみたいなもんです。私もさっそくインストールしてみました。(無料のライト版は月やMAPへの表示は使えません)
防寒対策
屋外にじっとしているので夏でもかなり冷え込みます。秋~冬の月食では想像以上に寒くなるため、「ちょっとやり過ぎてでは?」くらいの準備でちょうど良いです。足下の防寒対策もお忘れ無く。保険に予備のカイロなども持っておきましょう。
屋外の場合は待っている間に地べたに座るととても冷えるため、折りたたみ椅子など持っていくとなおよし。
バッテリー消耗にも気をつけて
皆既月食の撮影派長丁場となります。低温の場合はバッテリーの消費がいつもより大きくなります。予備バッテリーはしっかり準備しておいた方が良いと思いますよ!
最近のUSB給電できるカメラであればモバイルバッテリーを持っておくのも良いでしょう。相性があるので事前に給電出来ているかどうか確認するのも大事です。
まとめ:設定が分かっていれば誰でも撮れる!
ということで皆既月食の撮り方を具体的な設定を紹介しながらまとめてみました。たぶん今回の設定で撮れば大失敗は無いんじゃないかなと思います。
しっかり望遠レンズを使い、ピントを合わせて、決められた露出を守る。これだけでOKです。
天体ガチ勢になってくると赤道儀使ったり、マルチショットでコンポジットしたりといろいろ高度なワザを繰り出しますが、普通の入門カメラにWズームキットくらいのライトな機材でも皆既月食撮影は楽しめますのでぜひ挑戦してみて下さいね。
予行練習もおすすめ
月の撮影が初めてと言う場合は、欠けてなくても良いので今日や明日の夜に練習をしてみることをおすすめします。慣れない寒い屋外でいきなり超望遠+三脚使うと戸惑うと思うので。
後は天気が良くなることを祈りましょう・・・
その他月の基本的な撮り方は下記ページに詳しくまとめているので、撮影後の処理や設定値の根拠など知りたい場合は読んでみて下さいね。
動画でも解説してます!
YouTubeのstudio9 channelでも月食の撮り方の解説をしました!過去の月食の実データを使いながらターコイズフリンジの合成手順なども紹介していますよ!良かったらチャンネル登録してね!